有給休暇がないと言われた!付与条件を知り戦う基礎を作ろう
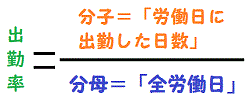
年次有給休暇は、労働基準法39条に書いてある通り、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、法に定める所定の日数が付与されます。
しかし実際には、「雇入れの日」がいつだったのか?「6箇月継続勤務」について、途中で一時退職した人はどうなのか?「全労働日」の正確な意味はどういう意味なのか?などで迷う点が出てきます。
その分かりにくい点のすき間を突くようなトラブルも後を絶ちません。実際の相談の中で、これら3つの条件を会社の都合のいいように取り扱って出勤したものとみなすべきところ欠勤扱いとし、その結果として有給休暇が与えられない、という不利益を受けた労働者の方もいるのです。
しかしあなたのケースが、3つの条件を満たしているかどうかは、以下で示す分析方法を学ぶと、独りでも判断しやすくなり、付与されなかった場合に自分自身で確認することができるようになります。
有給休暇の付与条件を知り権利が発生しているか否かを判断することは、有給休暇の戦いを始めるうえでの最初のポイントとなります。このページで戦いの第一歩を踏み出しましょう。
これら4つの過程をどのように行っていくのか?以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
有給休暇が付与される条件を知るため、まず労働基準法39条を読む
年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務した労働者に当然に与えられる大変重要な権利です。ここで労働基準法第39条1項を見てみましょう。
「使用者は、その雇い入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
つまりこの条文は、「雇い入れの日から起算して」「六箇月間継続勤務し」「全労働日の八割以上出勤」という3つの条件を満たした労働者に、使用者は法で定める数の有給休暇を必ず与えよ、と言っているのです。
この単純な条件についても、実は多くの解釈や意見の対立があり、実際の現場で多くの問題が発生してきました。
「雇い入れの日から起算して」についての分析方法
「雇い入れの日から起算して」の原則
起算日は、雇い入れの日、すなわち採用された日となります。
試用期間がある場合はどうでしょうか?時折、試用期間後の本採用日を起算日としている会社がありますが、あくまで仮採用日といえども、その日を起算日としなければなりません。
「雇い入れの日から起算して」についての二つの例外
例外1:使用者が特定の締切日を設ける場合
年次有給休暇の起算日は労働者が採用された日であるから、各労働者ごとに違うのが一般的です。起算日が違えば当然与えられる日(月)も違ってきます。各労働者ごとに有給休暇の付与日(月)が違う状態では、担当部署での有給休暇の管理業務が複雑になってしまい、付与に関わるミスも発生しかねません。
そこで、行政通達では、全労働者の有給休暇付与を一斉に行えるようにするため、特定の締切日(出勤率計算の日)を会社が独自に設けることを認めました。しかしそれでは、会社が定めた締切日の直前に入社した労働者は、締切日までに6箇月の勤務継続期間を満たすことができなくなり、次年度までもらえなくなってしまいます。通達はそのような不利益が当該労働者に降りかかるのを避けるために6か月間に足らない期間は、出勤したものとみなさなければならないと示したのです【基発昭和63・3・14】【基発平成6・1・4】(図表1)。
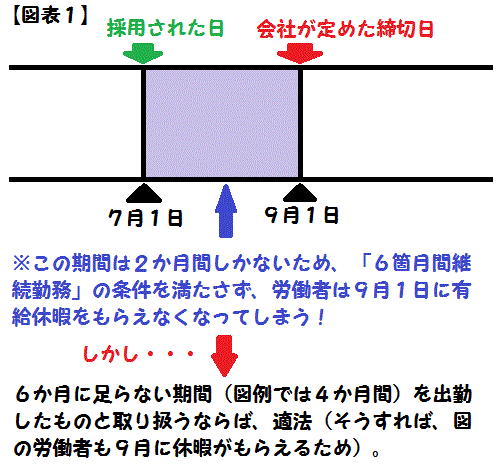
例外2:年次有給休暇の付与を半年繰り上げる場合
採用の日にいきなり有給休暇を与えることはどうでしょうか?普通は、採用後6箇月を経過したのちに有給休暇が10労働日与えられますが、それを半年早める、という方法です。
具体的に書きますと、採用日にいきなり5労働日の有給休暇を与え、採用日から6箇月後にまた5労働日、採用日から1年後に11労働日、採用日から2年後に12労働日・・・・という与え方です。【図表2】を見てください。
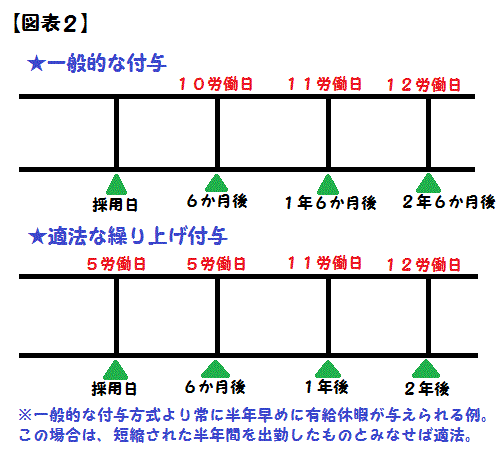
上図のような与え方は問題ない、とされています。なぜなら、この方法ですと、労働者は法で定められた付与方法より常に半年早く有給休暇が与えられるため有利だからです。この場合は、短縮された半年間を出勤したものとみなせば適法だとされています。
「6箇月継続勤務」についての分析方法
行政通達・判例(裁判例)は、それぞれ「6箇月継続勤務」の意味をどのように説明しているか?
行政通達が示す「継続勤務」
「継続勤務とは在籍期間をさし、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべき」【基発・昭和63・3・14】
「例えば定年退職後の嘱託勤務、法第21条各号該当者、一定月ごとに契約更新して6箇月以上に及んでいる臨時工等でその実態より見て引き続き使用されると認められる場合には、勤務年数を通算する」【基発・昭和63・3・14】
このように通達では、在籍期間を前提としながらも、対象期間が継続勤務となるか否かは、その中身、つまり実態で判断せよ、と言っています。
通達は、具体例として、定年後の嘱託職員・短期契約雇用者を挙げました。
判例(裁判例)が示す「継続勤務」
「労基法39条1項にいう「継続勤務」とは事実上の就労の継続を意味するものではなく、同一使用者のもとで一定期間被用者の地位を継続すること、すなわち労働契約の継続を意味するものと解する」【名古屋地裁・昭和46・5・24】
「労基法39条の『継続勤務』は実質的に労働者としての勤務関係が継続しているかどうかにより決すべきであり、定年退職後同一使用者に再雇用された場合であっても、定年退職により一旦断絶した前後の雇用関係の内容に、勤務日数が大幅に変化する等のことがあれば、継続勤務とはいえない」【東京地裁・平成2・9・25】
「1年間の期間の定めのある雇用契約を繰り返し更新し、途中中断することなく継続雇用されている者に対する労働基準法39条の適用については、これらの者は継続勤務したものとして所定の日数の年休を与えなければならず・・・」【東京地裁・平成9・12・1】
「馬券売場の馬券発売又は払戻し業務従事者のように、競馬開催期間が雇用期間とされ、在籍していない期間があり、1か月間に1日も就労しない実態があっても、競馬開催期間についての法令上の制限があることから、労基法39条1項の適用についてはこれを継続勤務として、要件を満たす場合には、年次有給休暇を請求する権利を有する」【東京地裁・平成7・7・12】
両者の示す定義の共通点としては、労働契約が結ばれている間、つまり在籍期間中は継続勤務と判断される、という点です。そして各個別事例ごとに判断材料となる事実を取り上げ、通算するか判断する、というスタンスです。
では以下で、よく問題として取り上げられる具体例について、見ていきましょう。
各具体的事例では、どのように判断されているか?
定年退職後に再雇用した場合
前掲の行政通達では、「継続勤務とは在籍期間をさし、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきであり、次に掲げるような場合を含む」とし、次のような場合として「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)。」と示しました。加えて「ただし退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断絶していると認められる場合はこの限りではない」と例外にも触れました。
しかしこの点について前掲の判例は「定年退職後同一使用者に再雇用された場合であっても、定年退職により一旦断絶した前後の雇用関係の内容に、勤務日数が大幅に変化する等のことがあれば、継続勤務とはいえない」という判断をします。
整理しましょう。通達と判例の考えをまとめました。以下の考えをもとに上から順に検討し、あなたのケースで勤務年数が通算されるかの目安をつけましょう。
- 継続勤務とは在籍期間をさし、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断する(この点は行政通達も判例も同じ見解)。
- 退職手当をもらって定年退職しその会社で嘱託として再雇用された場合、その前後の期間は引き続き労働関係が継続しているとして勤務年数を通算する。
- 定年退職と再雇用の間に相当期間が存している場合は、労働関係が断絶したものとして勤務年数を通算しない。
- 再雇用までの間に期間が空いてない場合でも、定年の前と後で勤務日数等で大幅な変化があるような場合は、継続勤務とみなさず、勤務年数は通算しない。
会社合併に伴い、労働者が合併会社に採用された場合
この場合、合併会社に採用された労働者の勤務年数は通算されると解されています。
もし会社合併の時当該労働者に退職金が支払われても、その事実だけをもって労働契約が中断された事実にはなりません。退職金は、使用者が一定の時期(多くは退職の時)に支払う義務を負ったお金であり、それを払ったからといってその時が「退職時」になるわけではなく、「先払いで払った」と扱われるだけだからです。
パート・アルバイトから正社員になった場合
この場合も、勤務年数は継続される、と解されます。
「パート・アルバイトから正社員になった」という事実は、単に「会社内での身分に変更があっただけ」に過ぎないからです。
パート・アルバイトから正社員に身分が変わる時に、一定期間の空白(例えば1~2か月)があったとしても、それが同一の使用者に採用される場合であれば、勤務年数は継続される、と考えられます。
労働組合の専従期間がある場合
在籍専従(会社に在職したまま、休職等の扱いにより組合活動に専従するケース)の場合は、その期間中は勤務年数に通算するように取り扱わなければなりません。
会社を退職して組合に専従する場合は、各人の具体的状況をピックアップし、それにより労働関係が継続しているか否かで判断する、とされています。
長期療養のために休職している期間がある場合
休職期間中にも労働契約が継続していれば、その期間は勤務年数に通算しなければなりません。労働契約の継続こそが、「継続勤務」となるからです。
「全労働日の八割以上出勤」についての分析
- 1.「全労働日」の定義をはっきりと理解する
- 2.式の分母と分子に含ませるべきか分かりづらい日を処理するための前準備として、「全労働日か否か、出勤日とみなすか否か」の視点で、4つの場合に分類する
- 3.労働基準法上問題となる様々なケースや法に基づく休暇・休日が、4つの分類のどこに分けられるかを知る
- 4.あなたのケースの中で分かりにくい日が、3つの場合分けの中でどこに入るかを判断し、そのうえで出勤率を計算する
1.「全労働日」の定義をはっきりと理解する
あなたのケースが「全労働日の八割以上出勤」を満たしているかどうかを判断するために、まずは「全労働日」の内容をしっかりと理解しましょう。「全労働日」の定義については、行政通達と最高裁判所の裁判例で、その内容に触れたものがあります。
- 「就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい」【基発・昭33・2・13】
- 「一年の総暦日数のうち労働者が労働契約上労働義務を課せられている日数」【最高裁判・平4・2・18】
分かりやすく言い換えましょう。あなたが会社からもらった、出勤日と休日が記載されたカレンダーなどを見て、出勤日とされている日が「労働日」となります。その「労働日」の総日数が「全労働日」となるのです。
時折、暦の上での休日以外の日の総数を「全労働日」としてしまう間違いが見受けられます。あくまで会社が定めた出勤日が「労働日」であり、その総日数が「全労働日」となるのです。
なぜ「全労働日」を正確に知る必要があるかといいますと、八割以上出勤したか否かの計算(以後「出勤率の計算」とします)にあたっての分母となるからです。ここで出勤率を計算するための数式を復習しておきましょう。
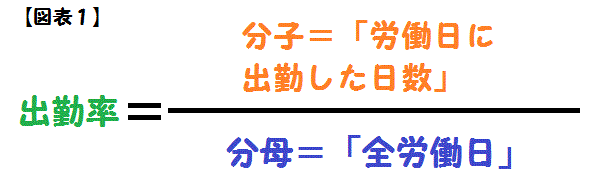
全労働日を把握しさえすれば、あとは、労働日に出勤した日を数えてそれを分子に当てはめれば、あなたの出勤率は分かることになります。
しかし実際には、分母(全労働日)として数えていいのか、または、分子(労働日に出勤した日数)に数えていいのか判断が難しい「日」または「出勤日」も出てきます。それが出勤率の計算を複雑なものにし、有給休暇付与に際して問題となるのです。あなたが出勤率を計算しようとこのページを見ているのも、判断に困る「日」があるから見ているのだと思われます。
では、以後のステップでその点も踏まえて説明しましょう。
2.式の分母と分子に含ませるべきか分かりづらい日を処理するための前準備として、「全労働日か否か、出勤日とみなすか否か」の視点で、4つの場合に分類する
上図の式の分母と分子に含ませていいかどうか分からない日を処理するためには、下の図を使って頭を整理することが有効です。
つまり、有給休暇の出勤率算定の対象となる期間のすべての日を、下の分類表に当てはめつつ整理していくのです。
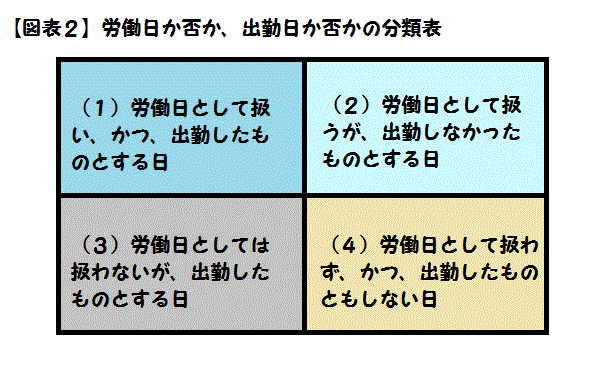
会社カレンダーや就業規則等で出勤日とされた日で、かつ普通に出勤した日は、何の迷いもなく(1)に含まれると分かるでしょう。
会社カレンダーや就業規則等で休日とされた日も、問題なく(4)に分類できます。
しかし先ほども少し触れたように、災害で休日になってしまった日や、出産が長引いて産前産後の法定休業日を超えてしまった日等の「イレギュラー日」の扱いこそが困るのです。会社側がそれらの日を自己の都合のいいように扱い出勤率を計算することで、労働者が不当に不利益を受ける問題が出てくるのです。
以下で、今まで多くの問題が起こり、それゆえ裁判や行政通達で判断が下された「イレギュラー日」を、【図表2】を見ながら整理していきましょう。あなたが今抱えている疑問を頭に入れながら読んでください。
3.労働基準法上問題となる様々なケースや法に基づく休暇・休日が、4つの分類のどこに分けられるかを知る
(1)に該当する場合(労働日として扱い、かつ、出勤したものとする日)
上図(1)に該当する日(労働日として扱い、かつ、出勤したものとする日)は、以下の3つです。
- 有給休暇を取得した日
- 労働者が正当な理由なく、使用者から就労を拒否された日
- 産前の休業が出産の遅れで6週間を超えた場合、その超えた日々
有給休暇を取得した日
労働基準法に定められた労働者の権利を正当に利用した日であるため、その日を出勤したものとみなさないことは有り得ません。当然に上図(1)の中に入る日となります。
労働者が正当な理由なく、使用者から就労を拒否された日
労働者が正当な理由なく就労を拒否された日とは、どのような日でしょうか?
分かりやすく言い換えれば、使用者の理由なき、もしくは明らかに違法な扱い・措置・辞令・命令等で、会社に出勤させてもらえなかった日(出勤できなかった日)が考えられます。具体的に示すならば、以下のような日が挙げられるでしょう。
- 裁判所の判決により解雇が無効となった場合、解雇の辞令を受けて出勤しなくなった最初の労働日から、復職日直近の労働日までの日々
- 労働委員会の救済命令を受けて会社が解雇の取り消しを行った場合
産前の休業が出産の遅れで6週間を超えた場合、その超えた日々
労働基準法による産前産後の休業期間中は、出勤率の計算に当たっては当然出勤したものとして計算されます。
しかし産前6週間の休業期間は、あくまで「出産予定日」を基本に設定されています。もし出産が予定日より遅れた場合は、当然6週間を超えて休むことになります。行政通達は、その超えた日についても、出勤率計算に際しては、「出勤」として取り扱うように示しました【基収・昭23・7・31】。
※◇有給休暇Q&A ~出産の遅れで産前の休暇が6週間を超え、その日数分が欠勤扱いとなって今年分の有給休暇がもらえなかったが、それは違法ではないのか?参照。
(2)に該当する場合(労働日としては扱うが、出勤したものとしない日)
(2)の日と判断されることは、出勤率計算にあたっては労働者にとって不利なことと言えるでしょう。よって、(2)に分類される日の特徴としては、休んだことについて労働者に何らかの帰責性(責められるべき点)が見受けられます。
分かりやすい例ですと、「正当とみなされない同盟罷業(ストライキ)その他の正当とみなされない争議行為で、労務の提供をしなかった日」が挙げられます。
(3)に該当する場合(労働日としては扱わないが、出勤したものとする日)
(3)に該当する日はそもそも存在しません。よって、このケースは考えなくてよいでしょう。そのため、分類表の分類数は、3ということになります。
(4)に該当する場合(労働日として扱わず、かつ出勤したものともしない日)
裁判例・行政通達で具体的に指摘があったものを以下に挙げましょう。
- 不可抗力による休日 ※後述
- 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 ※後述
- 正当な同盟罷業(ストライキ)その他正当な争議行為により、労務の提供をしなかった日
- 所定の休日に労働した日
- 生理休暇を取った日
- 慶弔休暇の日
不可抗力による休日
「不可抗力」とは、天災事変・避けられない外的な犯罪行為等のことを指します。不可抗力による休日とは、これらの不可抗力により(就業場所の破壊やライフラインの断絶による操業不能等で)就労が不可能となった日々のことを言います。
使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
売上の減少にともなう生産調整による休業等のことを指します。これらの日々は、労働者が働く意思があっても会社側の都合で拒否をしているわけであるから、全労働日に含め、かつ出勤したことにする、という結論を招きそうです。
しかしそこで、使用者と労働者の衡平の観点から修正が入り、通達は、これらの日々は「全労働日に含まず、かつ出勤した日ともしない」という判断を示しました。
4.あなたのケースの中で分かりにくい日が、4つの場合分けの中でどこに入るかを判断し、そのうえで出勤率を計算する
ここまで見てきたら、後は自分のケースをもう一度見直します。
明確に分類できるものから分けていき、最後に分かりにくいものを分類を参考にしながら分けていきます。
どうしても分からないものは、労働基準監督署の総合労働相談所で尋ねるといいでしょう。労働法に明るい相談員に、匿名で無料で相談できます。
どのように扱ってよいか分からない日がある場合、その日をあなたにとって都合のいい分類で分けた場合と、都合の悪い分類で分けた場合の二つのパターンで計算します。分類の選択を変えることで出勤率が8割を上下するような方は、万全を期すためにも相談所に行って確認をし、その後会社に質問をしましょう。

